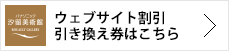1.ビーダーマイヤーのインテリア、工芸、モード作品
ビーダーマイヤー様式の特色は、家具や工芸、モードにおいて一貫して簡潔さ・実用性・抑制の美に表れています。
例えば、マホガニーやクルミなど上質な木材と、卓越した職人技によって仕上げられた、椅子やテーブル。幾何学的で簡潔な造形が実用性を際立たせる銀器や陶磁器、ガラス作品。節度のある装飾を重視し、身に着ける者の魅力を引き立てるドレスとジュエリー。いずれも私的空間への美学と丁寧な手仕事に支えられた、生活に根ざしたモダンな造形で後のモデルとなりました。
2.クリムト、ココシュカによる肖像画や、ホフマン、モーザーらによるモダンデザインの名品
オットー・ヴァーグナーの構造美を備えた郵便貯金局の家具、初期ウィーン工房による幾何学を強調したラディカルな銀器や、美しい統一意匠のテーブルウェア、細工の妙技が光るジュエリーやガラスビーズの装身具に加え、サナトリウム・プルカースドルフのための家具も並びます。
これらの作品群には、職人の高い技術に、合理主義と装飾性が響き合うデザインが展開され、ウィーン世紀末が志向した芸術と日常の総合を鮮明に伝えてくれます。さらに、グスタフ・クリムトによる《17歳のエミーリエ・フレーゲの肖像》とオスカー・ココシュカによる《アルマ・マーラーの肖像》は、本展のハイライトの一つになるでしょう。
3.ダゴベルト・ペッヒェ、マリア・リカルツらによる、ウィーン工房後期の装飾性豊かな工芸作品
ウィーン工房の活動後期には、装飾性豊かな作品が複数の部門で生み出されました。その筆頭デザイナーというべき、ダゴベルト・ペッヒェによる作品はチューリヒ支店の箪笥をはじめ、陶磁器、ガラス、金工、レースなど多数登場します。このほか、マックス・スニシェクの斬新な抽象模様のテキスタイルによるドレスや、同じモード部門で活躍したマリア・リカルツのテキスタイルおよびドレスのデザイン画やビーズネックレス、バッグなど。さらにヒルダ・イエッサーやレニ・シャッシュル装飾による絵付けガラス作品や、ヴァリー・ヴィーゼルティアやグドルン・バウデッシュの軽快な遊び心が効いた陶磁器製花器、繊細な描線のフリッツィ・レーヴによるテーブル・カードなど、在籍した女性デザイナーの作品を様々ご覧いただきます。